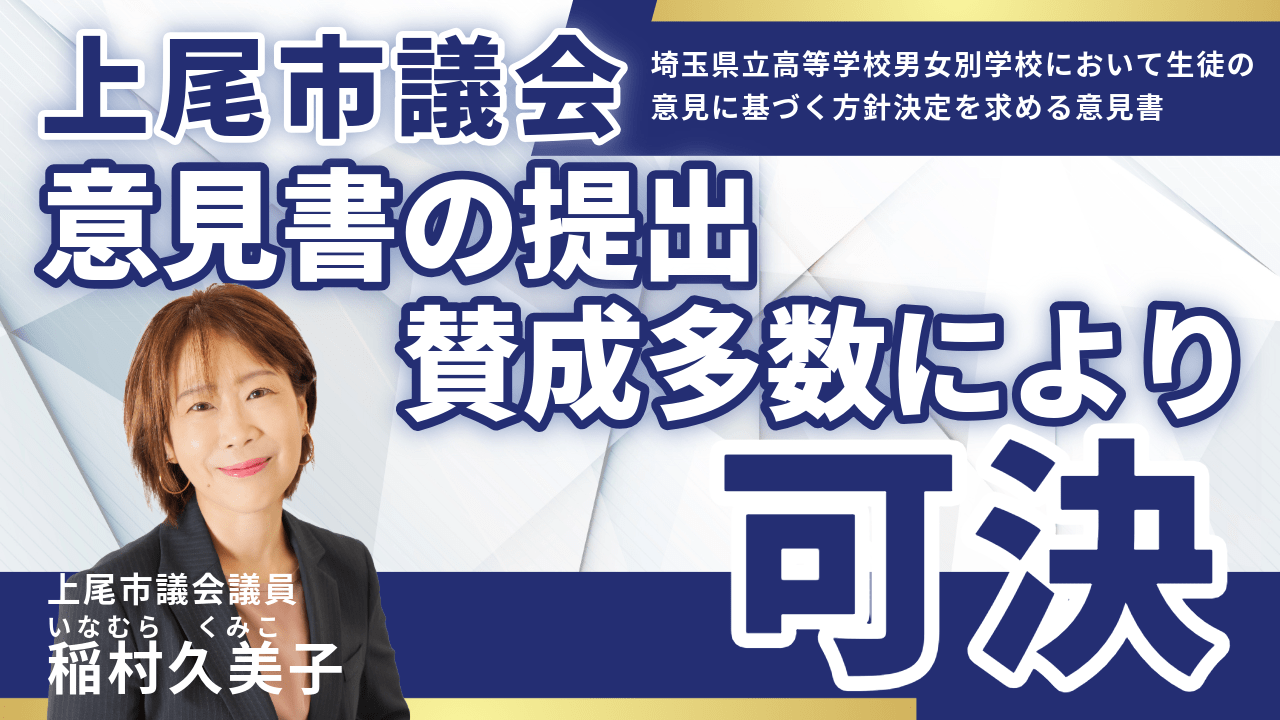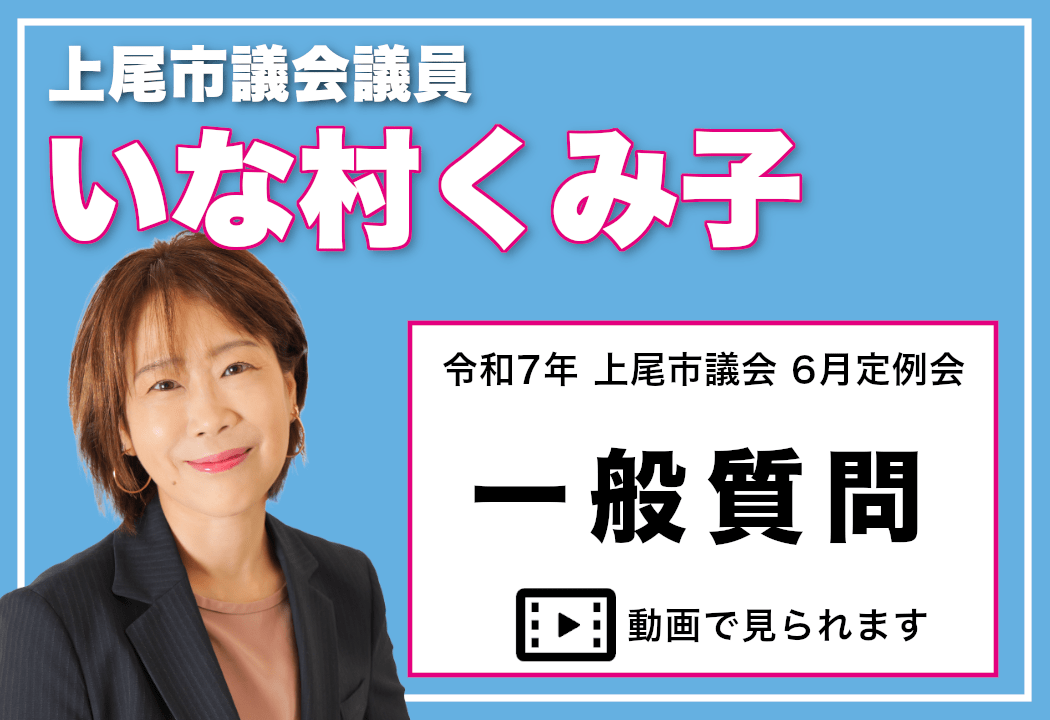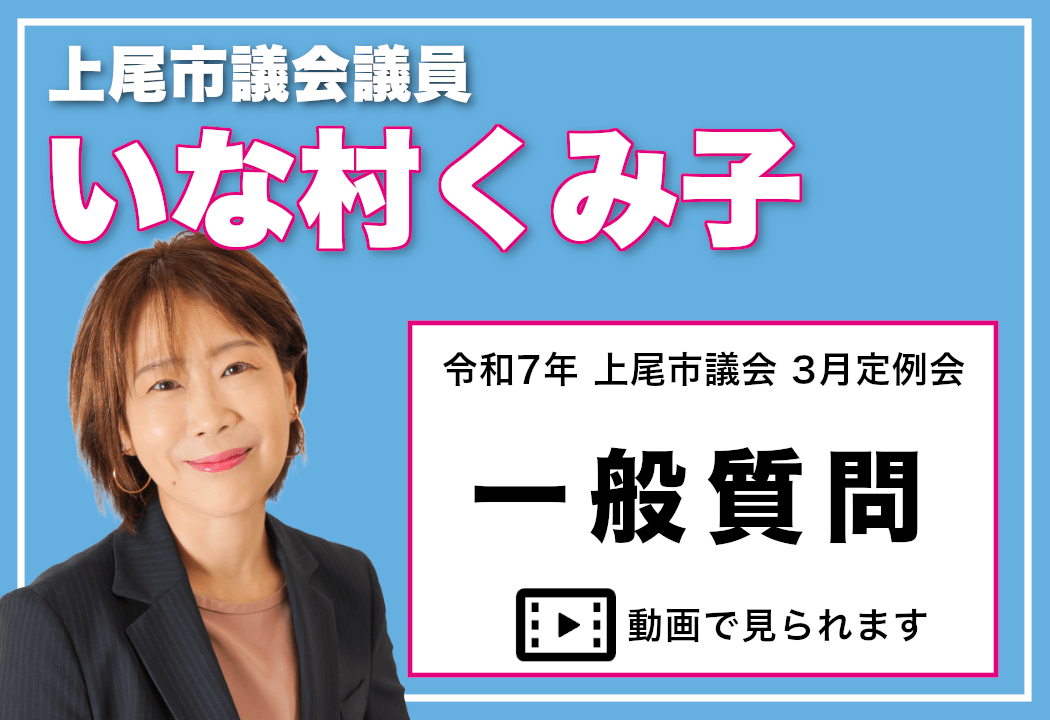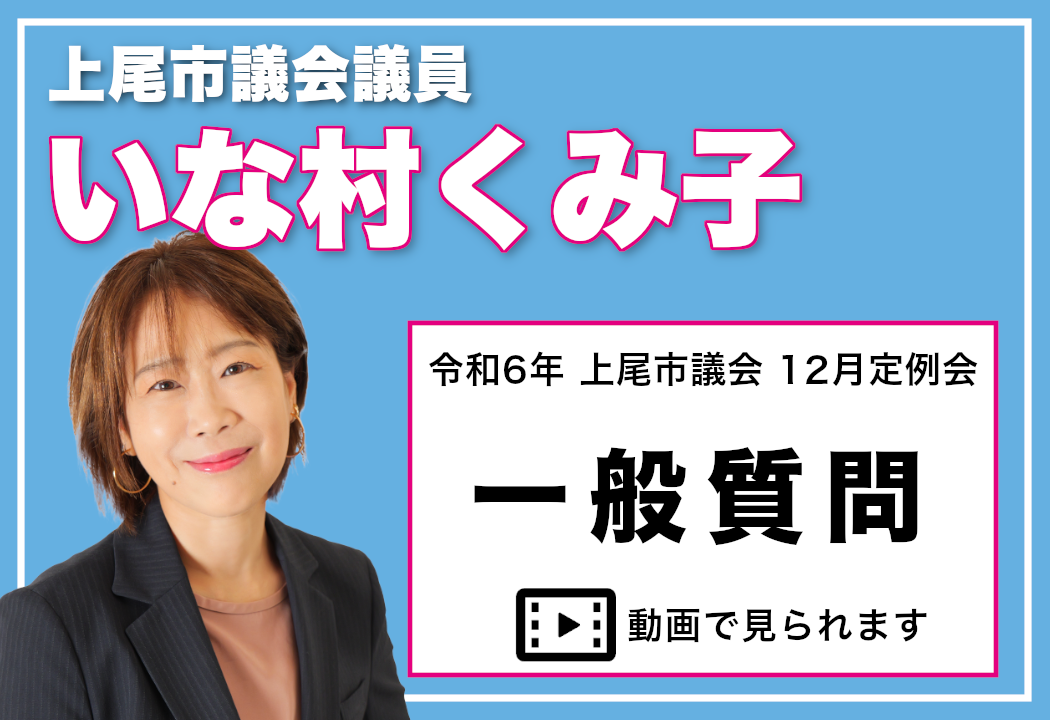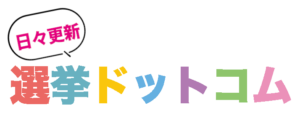上尾市議会議員 稲村久美子です。
今回は「介護」「災害対策」「ネーミングライツ」の三本柱で一般質問をやらせていただきました。
質問事項
項目をタップ(クリック)で移動します

❶ 要介護者および家族への支援について
「要介護者」とは…介護保険法の要介護と認定された者①要介護状態にある65歳以上の者、②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因となった心身の障害が特定疾病によるもののうち、在宅の者をいう。
「要介護状態」とは…負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。
「要支援者」とは…介護保険法の要支援と認定された者①要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者②要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれのある状態となった原因となる心身の障害が特定疾病によるもののうち、在宅のものをいう。
質問1-1)
市内の要介護者の人数を教えてください。

答弁1-1)
令和6年12月末現在、上尾市の被保険者のうち要支援要介護認定者数は、要支援1が1,210人、要支援2が1,558人、要介護1が2,822人、要介護2が2,468人、要介護3が1,674人、要介護4が1,379人、要介護5が866、合計で11,977人でございます。

要介護4、5というと、普通に生活していこうと思っても人手がないと生活していくことができない方だと思います。
うちの 母は、昨年秋に入院した時はたしか要支援1で、出てくる時には要介護5です。本当にもう全介護ですね。食事からトイ レ、もちろん一人ではできません。ベッドの上から降りられない状態だったんですけれども、そういう方が、約2,000人 は上尾市内にいらっしゃるということなんですね。
では次の質問にまいります。

質問1-2)
各種支援を受けるのに必要な要介護認定の受け方、手続きのやり方を教えてください。

答弁1-2)
要介護認定の手続きの方法でございますが、介護保険被保険者証や健康保険者証をご用意いただき、高齢介護課へ直接申請するほか、お住いの地区を担当する地域包括支援センターへの申請代行を依頼することができます。

それでは次の資料(上尾市ホームページ掲載:介護保険の利用の手引き「上尾の介護保険」)をご覧になってください。

クリック・タップでPDFが開きます
こちらは上尾市で配っているリーフレットです。本当に良く出来ています。これを見ますと、手続きの仕方であったり、介護保険の利用には相談が必要です、なんてことも書かれています。
ただこれ、細かすぎてしまって、最初にまず何をしたらいいのか分からないっていうことがあって。手帳すらまだ取ってい ないという方が近所にね、80 歳後半でもいらっしゃる。まずは、一度相談に来てください、ということをずいぶんお話させていただきました。
うちが介護やっているということで、ご近所の方とお話することも多かったので。

質問1-3)
何をしたらよいか分からず高齢になってしまい、手続きをしていない場合、自力でそれを行うのが困難なケースがある。
誰がサポートするのか、また、家族がいない場合はどうしたらよいのでしょうか。

答弁1-3)
介護に関する総合相談窓口として、地域包括支援センターがございます。
地域包括支援センターは市内 10ヵ所に設置されておりますので、お住いの地区の地域包括支援センターへの来所や電話によりご相談をいただくことで、各種 手続きの支援を受けることができます。
なお身体の状態などから、来所が困難な場合には、地域包括支援センターの職員が、自宅を訪問し、支援を行っております。

「まず最初にどうしたらよいか」この点をもう少し分かりやすくお知らせしてほしい、と要望を入れました。
質問1-4)
要介護者およびその家族が受けられる市独自のサービスはどのようなものがあるのでしょうか。

答弁1-4)
市独自のサービスといたしましては、介護保険の認定が要介護4または要介護5の高齢者のうち、在宅で介護を受けているご本人に対しましては要介護高齢者手当や、要介護高齢者に紙おむつを給付する制度があるほか、在宅で介護している方を対象とした、要介護高齢者介護者慰労金の支給制度がございます。
また、在宅時に病気による発作などが起きた場合に、ボタンを押すだけで緊急通報センターに繋がる緊急通報システムの貸与のほか、徘徊する高齢者を在宅で介護している方に居場所を探索するための端末機貸与する、徘徊高齢者等探索サービスなどがございます。

質問1-5)
この紙おむつ券について、該当者への周知が十分でないと感じました。
実際はお手紙を送ってくださっていたそうなのですが、これはどのような方法で行っているのか、詳しくお教えください。

答弁1-5)
要介護認定の結果を通知する際に、市独自の福祉サービスについてご案内チラシを同封しているほか、地域包括支援センターと連携し、必要としている方が利用できるよう周知を図っております。

この紙おむつ券を受給できるというのが、住民税非課税世帯という、限られているので、なかなかね、そういうことを聞きづらいということを、現場の声としてお聞きしました。
年金生活している場合ですと、紙おむつも高いですし、その分助かりますから、もっともっと知られていけば、と思います。

質問1-6)
この紙おむつ券の使い方が分かりづらいという指摘があります。薬局でも使用方法の問い合わせがある、ということをお聞きしました。
紙おむつ券の裏面に明記されているのですが、私の年齢でも老眼などでよく分かりづらい。ですからこれが高齢者には分かりにくいんですね。
今よりも分かりやすい明記の仕方ができないでしょうか。

答弁1-6)
現在対象者への紙おむつ券を送付する際、使用方法についてのご案内を同封しております。
また、紙おむつ券の裏面の記載内容につきましては、今後も利用者のご意見などを踏まえ、字体やデザインの変更も含め、検討してまいります。

質問1-7)
次は、在宅で介護をしている方についてご質問いたします。
仕事や育児がある方への配慮というのは、あるのでしょうか。

答弁1-7)
要支援要介護者本人の心身等の状況や生活環境のほか、家族などの介護者の状況に応じて、介護保険制度や、市独自の支援の中から、必要な居宅介護サービスを利用していただくことが可能となっております。

質問1-8)
本人及び家族への心のケアはあるのでしょうか。

答弁1-8)
介護における本人や家族の悩み等につきましては、地域包括支援センターやケアマネージャーが相談をお受けしております。
そのほか、本市の取り組みといたしまして、介護者が抱える介護の悩みや不安について話し合う場として、介護家族会を毎月開催しておりますほか、市が後援している市民の自主グループとして「介護者支援の会あげお」があり、これらの介護者サロンにおいて、介護者同士が自身の悩みを話し、共感しあうことで、孤立感の緩和等を図っております。
また、本人が認知症の場合には、本人同士が主になって自らの体験や希望、必要としていることを語り合う場である、本人ミーティングを開催しております。

問題として、実際に相談に行けないということがあるかと思います。
例えばうちの場合ですと、母がもういつ死ぬか分からない状態で退院してきたので目が離せませんでした。
乗り切れたのは、家族が多かったことと、自費でも良いと割り切ったからです。保険で使える範囲だけではとても 24 時間目が 離せない人間を在宅看護は無理です。そうなると介護者は夜中寝られないわけです。
ショートステイがあるじゃないかという声もあるかと思うんですが、最後はショートステイにも預けられない状態になるんです。
その状態になったときが 一番きついわけです。そういうときにどこで救われたかというと、やはり家に来てくれるヘルパーさんや訪問看護師さんとお話をしたりということなんです。
それから、今回は質問に入れられなかったのですが、入浴の問題があります。
最後の方のうちの母の望みは「お風呂に入りたい」ということでした。が、訪問入浴は週に一回しか利用出来ませんでした。
自費でもいいので、とお伝えしまし たが、そもそも空きがなくて出来ないと。 ショートステイもそうでしたが、利用したいと思ってもなかなか空きがないんです。
そういう事業者さんを育てていくということで、予算を市でもとっていきましょう、というお話が予算委員会でも出ていました。
在宅介護を勧めているわけじゃないですか。お家で看取る、お家で亡くなるということを。
勧めている以上はもっときち んと体制を整えていただきたいです。
お家での介護や看取りを進めていくためにはやはり事業者さんですよね。
ヘルパ ーさんであったり訪問看護師さんであったり。あとは往診のクリニックであったり。これが選べる状態っていうくらい、沢山育てなければいけない。
ここに対して市は支援をしていっていただきたいと、お願いしたいです。

❷ 災害時について
明日は東日本大震災から 14 年経ちます。
こちらは以前私が撮った写真です。震災 があって、私は 3 月 31 日に宮城の石巻市に向かいました。




3 枚目の写真、これは 彼女たちのお家があった場所です。ここに写っている子たちとは今でも連絡をとっています。
一昨日も電話で「写真を使っ てもいい?」「いいよー」なんてやり取りをしたんですが。この子たちはもう皆成人して、働いています。
当時、私はここで物資を広げさせてもらって、現地の方々に配りました。その時に子供たちの方から話しかけてくれたんです。
「もっと人がいる所があるから来て」 って。小学校の避難所でした。鹿妻小学校です。
そこからが私のスタートで、それから何年かずっと復興の支援であったり、復旧に関わらせていただいておりま す。
東北関東草の根支援プロジェクトというのを私自分で立ち上げておりまして、当時仲間内に声をかけ、物資やお金をとにかく沢山集めて、主に石巻にですね、通っておりました。
こちらの写真をご覧ください。


これ、避難所の体育館(宮城県鹿角小学校)に敷いてある畳です。
当時避難さ れて来た方に聞いたところによると、最初は体育館の冷たい床に寝ていたそうなんですが、あるとき八代亜紀さんがいらして畳を寄付してくださったそうです。
この仕切りの中で、皆生活していました。年頃の女の子もですよ。着替える場所と かもそんなになかったんです。
ここに、私の後輩のエステティシャンの子と行って、なにか気分の上がることをやろうと、お顔と手のマッサージを避難者 の方にやらせていただきました。
他にもあちらの学生さんや若い方から「元気になるイベントをやっていただけませんか」ということで、仮設住宅ができてからはそちらで向こうの芋煮会の方々とハロウィンイベントをやったり、フリーマーケット をやったりしています。
前置き長くなりましたが、災害というのは思いもよらない大きさ、事が起こるわけです。
そういうわけで大項目 2 を質問 させていただきたいと思います。

質問2-1)
市内の指定避難所は、どこに、いくつあるのでしょうか。
答弁2-1)
市内小中学校や県立学校、公共施設など、市内全域に48ヶ所指定しております。
質問2-2)
48ヶ所あるとのことですが、どこにあるか一覧で確認することは可能でしょうか。
また、収容人数もお教えください。

答弁2-2)
指定避難所の現地全てに標識を設置しております。
また、市で発行している防災ガイドブックや、市ホームページに、指定避難所の一覧を掲載し、周知しております。なお、防災ガイドブックは令和4年2月に全戸配布しているほか、転入世帯に対して転入手続きの際に必ず配布しております。
収容人員につきましては、48ヶ所の避難所全体で、避難想定人員の11,613人の収容が可能となっております。

質問2-3)
障害や疾患など、事情を抱えた避難者の方への配慮というのはどのようなものがあるでしょうか。

答弁2-3)
本市では、避難行動要支援者名簿を作成し、高齢の方や、障害をお持ちの方など、避難に支援が必要な方をリストアップするとともに、情報提供にご同意いただいた要支援者分の名簿を平時から地域の自主防災会等にお渡しすることで、避難支援に役立てております。
また、指定避難所には通常の避難スペースのほか、空き教室など、配慮が必要な方を受け入れるためのスペースを、各避難所運営会議にて指定しております。
なお、指定避難所での生活が難しい場合、福祉避難所に二次避難をする形となります。

質問2-4)
福祉避難所への対象者および福祉避難所が近隣にない場合、また、定員超過などを想定した受け入れ体制の拡充についてはどのようにお考えでしょうか。

答弁2-4)
福祉避難所への避難対象者につきましては、スクリーニングシートを活用して、指定避難所での生活に必要な支援内容等のヒアリングをおこない、福祉的な配慮が必要とされた方を、受け入れ可能な福祉避難所にご案内することとなります。
災害時に備え、福祉避難所の受け入れ体制の拡充にご協力いただけるよう、引き続き施設に働かけてまいりたいと考えております。

障害がある方ですと、その状態が一定期間続いているため、すでに聞き取りが出来ていたり、支援がすでに届いている場合もあります。
ですが、介護の場合、急激に悪くなったり、その状態が日々変わっていきます。二日前は話せた人が今日は死にかけているなんてこともある。母の介護をしながらずっと考えていたんですね。今、大地震があったらどうやってお母さん連れて逃げよう、なんてことを家族とも話しました。寝たきりの人間、家にストレッチャーなんてないわけです。長時間の移動が厳しい方もいる。そうなってくると、やはり災害時には病院を頼ることになるのかな、と。
ですが災害時というのは病院も一杯ですよね。どこも人手が足りなくなるでしょうし。そういったことも我々は想定しなければならない。
その状態で、どれだけのことが出来るかと考えたときに、沢山準備をしていても、それでも足りないくらいのことが起きるわけですね。そうなった場合、動けない方をどうしていくかというのは、今後の課題ではないかと思います。

質問2-5)
昨年、長時間停電が上尾市であったと思います。自宅が浅間台なのですが復旧したのがほかのお宅よりも最後の方だったんです。
(夕方停電になって)電気が使えるようになったのが23時頃だったと思います。
昨年のような長時間停電の場合、在宅介護者の人工呼吸器、酸素吸入器等への対応はどのようにお考えでしょうか。

答弁2-5)
災害等による長期停電時においても、人工呼吸器や在宅酸素等を使用して在宅で介護を受けている方が、安心して療養を続けるためには、平時からの非常用電源の確保や、医療機関との連携が必要であるとされています。
そのため日頃からの備えの周知を図っているところでございます。なお一定の障害要件を有し、在宅で常時人工呼吸器を使用している方につきましては、障害福祉サービスにおいて、人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリーを日常生活用具の補助メニューとしております。

稲村久美子から行政への要望!
質問2-6)
各地区で備蓄品について、市では把握しているんでしょうか。

答弁2-6)
自主防災会は、自主的な活動団体であるため、詳細な備蓄品目や備蓄数の把握はしておりませんが、各自主防災会から、自主防災活動補助金の実績報告を提出していただいており、備蓄品等の購入品について報告を受けております。

地区の役員さんというのは他の方に代わっていってしまうものですので、使い方等も市のほうからしっかりと指導をしていただければと思います。
一年に一度備蓄品の点検や指導をしてくださっているとのことなのですが、それとは別に要望があった場合は、対応をお願いしたいと思います。

質問2-7)
ペットと同行して避難できる場所はありますか。

答弁2-7)
市内指定避難所48ヶ所のうち、特別な支援を要する児童生徒が通う県立学校以外の、47ヶ所でペットの受け入れを行っております。

質問2-8)
ペットであれば、どのような動物でも受け入れてもらえるのでしょうか。

答弁2-8)
市内指定避難所では小動物・鳥類で、ケージやキャリーバッグでの避難が可能な動物を受け入れております。
そのため、大型の動物や、特別な管理が必要となる動物に関しましては避難所での受け入れは困難となります。

質問2-9)
避難所ではどのような環境でペットの受け入れを行っていますか。
また、避難所で静かに過ごすこと、ケージの中に入っていることが難しい動物の受け入れは可能でしょうか。

答弁2-9)
市内指定避難所では、原則として人の居住スペースとは分離してペット専用スペースが設けられております。
ペットの管理は、飼い主の責任で行っていただきますが、飼い主でも制御できない場合は受け入れをお断りする場合がございます。
そのため、平時からの準備として、ペット用品の備蓄、健康管理、所有者の氏名・連絡先を明示していただくこと、また、ケージやキャリーバッグでの避難となるため、嫌がらないよう常日頃から慣れさせておくことが必要でございます。

こういうことをきちんと、例えばペットショップであったり、動物病院であったりで、上尾市としては災害時このような対応をしますから、皆さん準備をしておいてください、と周知できるようにしてほしいと思います。

“建物内部における家具・物品等の移動、転倒、飛散等や、屋根を含む天井の落下により負傷者が発生し、また人々の避難が困難となった。“
引用元「内閣府防災情報」
こちらは阪神淡路大震災をもとに作った資料です。
内閣府防災情報のホームページから引用しました。
どういうことで非難が困難になったか、ということですね。
次の資料、これは阪神淡路大震災の死亡理由です。

国土交通省近畿地方整備局ホームページより
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/daishinsai/1.html
No Data Found
埼玉県は内陸部ですので、こちらが参考になるのではないかと思います。
ご覧の通り、圧死された方が一番多いです。
焼死された方も多いのですが、これはやはり家屋に埋まってしまったり、抜け出せなかったりしてそのまま焼死してしまったという方が多かったと思われます。

質問2-10)
高齢者宅の大型家具について、防災面からの支援があったら教えてください。

答弁2-10)
令和7年度当初予算におきまして、65歳以上で構成する世帯や避難行動要支援者等を含む世帯を対象に、家具転倒防止器具の費用に加え、取り付けにかかる工事費に対し1万円を上限に、補助する事業費を計上しております。
3月定例会で予算成立後、補助金交付要綱を制定し、速やかに事業を実施してまいります。

この件は以前、矢口議員もやっていたかと思うのですが、今回はプロに対して依頼し、壁に固定してもらうことに対して補助金交付とのことで、ありがとうございます。
私の実家もそうなのですが、高齢者のお宅って世代的に大型家具が多いんですね。食器棚だったり、箪笥の立派なものがあったり。そうしますと、震災時転倒などで避難が難しくなってしまうんです。
ですので、今回費用の補助、とても素晴らしいのですが、そのうえで、高齢者宅の大型家具の処分も支援していただきたいと思います。
「外に出せないから捨てるに捨てられない」という話を聞くんです。西貝塚に連絡すれば粗大ごみとして引き取ってはもらえるのですが、それは玄関先までは自分で出しておかないといけないんですよね。
ですので、ここに関してもどんなことが出来るのか、今後も考えて頂ければと思います。

❸ ネーミングライツについて
質問3-1)
募集方法の違いについて教えてください。

答弁3-1)
ネーミングライツパートナーの募集方法は、特定募集型と提案募集型の2種類ございます。
特定募集型は、愛称を付す施設や契約期間、ネーミングライツ料の下限などを市が指定する募集方法でございます。
提案募集型は、法人から愛称を付す施設や契約期間、ネーミングライツ料等を提案していただく募集方法ですが、金銭以外に役務の提供や物品の納入などの提案をいただくことも可能でございます。

質問3-2)
ネーミングライツの募集は、どこで確認ができますか。

答弁3-2)
ネーミングライツパートナーの募集については、広報あげおに掲載するとともに、ネーミングライツ事業の募集期間中に、ホームページにおいても募集要項等を掲載しております。

質問3-3)
金額の設定の根拠について教えてください。

答弁3-3)
特定募集型については、愛称を付す対象施設ごとに、類似する他市の施設の規模や利用者数などを勘案して金額を設定しております。
提案募集型につきましては、法人から金額を提案していただくものではございますが、ネーミングライツ事業に係る職員の人件費等を勘案し、提案金額は10万円以上とさせていただいています。

質問3-4)
10万円という最低価格は安すぎるのではないでしょうか。

答弁3-4)
地元企業をはじめ、多くの法人が本市のネーミングライツ事業を活用できるよう、10万円以上と設定しています。

地元の企業、特に中小企業も利用しやすいように、という設定金額で今回あることが分かりました。
このことは、市民の皆さんにお知らせしていくべきだと思います。そうでないと、「なぜこんなに金額にバラつきがあるのか」と疑問に思われることもあるでしょう。

質問3-5)
名前変更による諸経費、パンフレットや看板ですね、これについてはどのようになっておりますでしょうか。

答弁3-5)
看板の設置に係る諸経費や、パンフレットの再印刷の費用など、愛称を付すことによって生じた経費については、ネーミングライツパートナーが負担することとなっております。

質問3-6)
看板を着けるにあたってのルールはあるのでしょうか。

答弁3-6)
ネーミングライツパートナーの公募の際は、愛称を付す対象施設ごとに看板の設置個所やサイズ等について、一定の条件を定めております。
また、看板の構造や設置方法等につきましても、本市と協議の上、ネーミングライツパートナーに設置していただくこととなっておりますので、景観を損なうような看板が立つことはございません。

質問3-7)
パートナー切り替え時は、看板や壁画等、原状復旧することとなっているのでしょうか。

答弁3-7)
契約が終了する際は、ネーミングライツパートナーの費用で原状復旧を行うものとしており、看板等の撤去等につきましては、ネーミングライツパートナーが負担することになっております。
なお、契約更新の際は、ネーミングライツパートナーが設置した看板を引き続き使用することが可能です。

質問3-8)
愛称のつけ方にルールはないのでしょうか。
元の名前を残すべきではありませんか。

答弁3-8)
募集に当たっては、法人の命名の自由度を高めるとともに参加意欲等を妨げないようにするため、愛称に「あげお」という名称を含めることなど、一定の条件のみを定めております。
一方で、公募によりすでに市民愛称がついている都市計画道路などは、その市民愛称を含んだ愛称とすることとしております。
今後、新たな募集をする際には、市民の方に愛着を持っていただけるよう、愛称のルールを検討してまいりたいと思います。

沢山の地元の方に利用していただきたい、愛着を持っていただきたいということですが、だからこそ、ルールをしっかり定めておくべきだと私は考えております。
ルールがあることで揉めることも少なくなりますし、何より市民の方に不安を抱かせてはいけないと思います。また、あくまでも「愛称」であって、正式名称を変更するわけではないということなのですが、ここも市民の皆さんに伝わっていないのではないでしょうか。
こういった目的の事業です、ルールもあります、ということを、我々には説明義務がありますよね。
市だって予算、歳入、決まっています。何かやろうとしたらお金が必要になります。自分たちでその分を作り出していこうというのはこれからも必要なことだと思います。
そのうえで、ルールを定め、市民の皆さんにお伝えしていくことが、私たちの仕事かな、と考えています。
と、いうことで一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

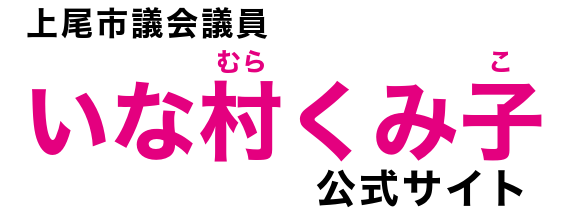
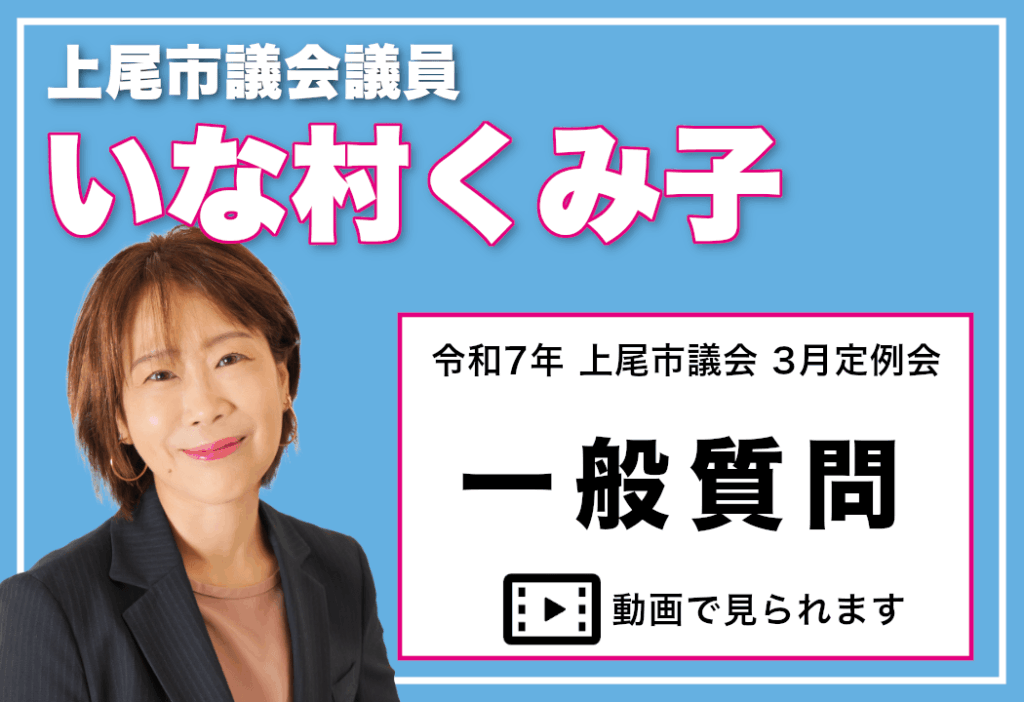
市政に対する政策要望書の提出.png)