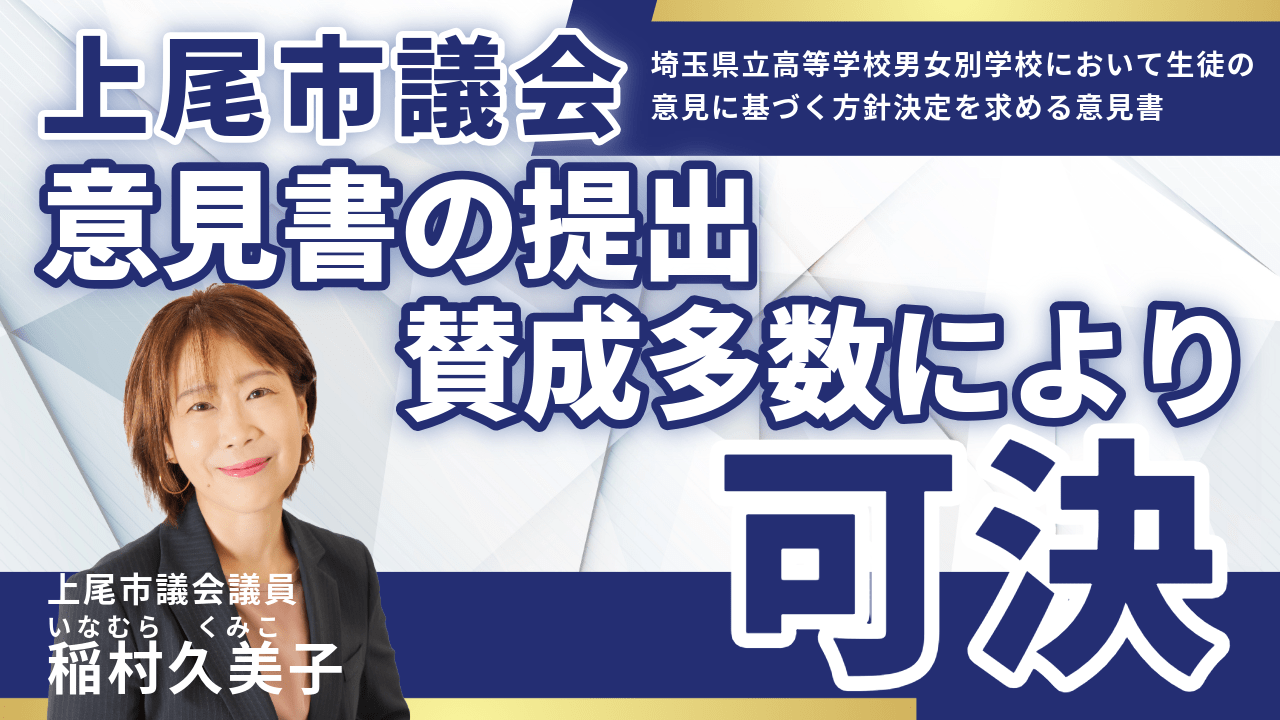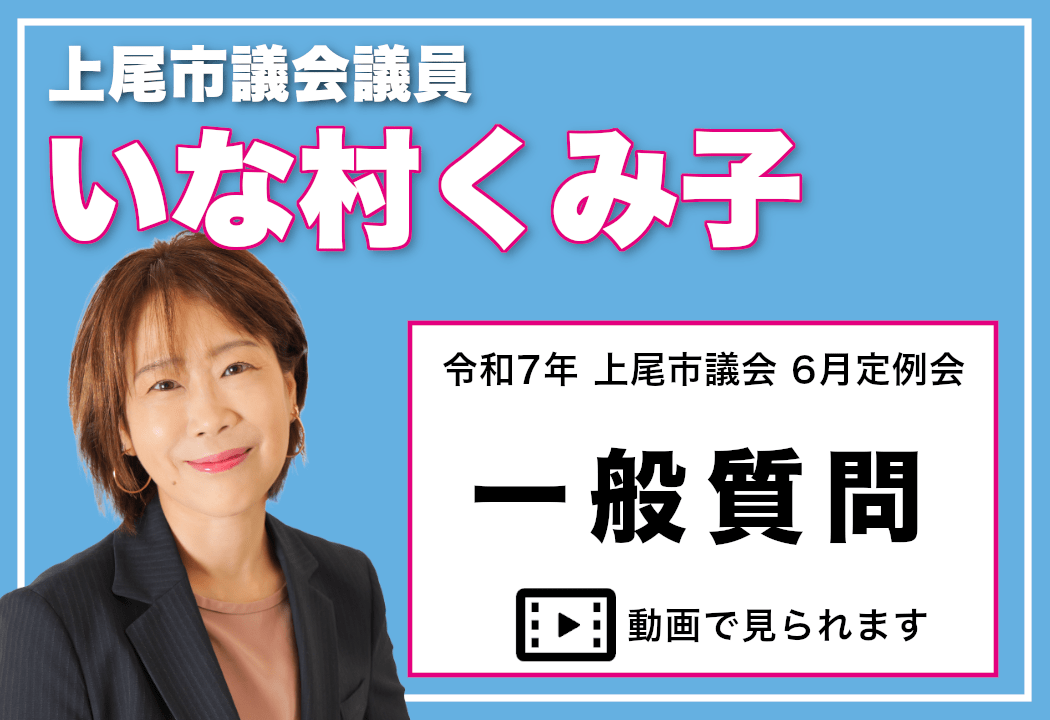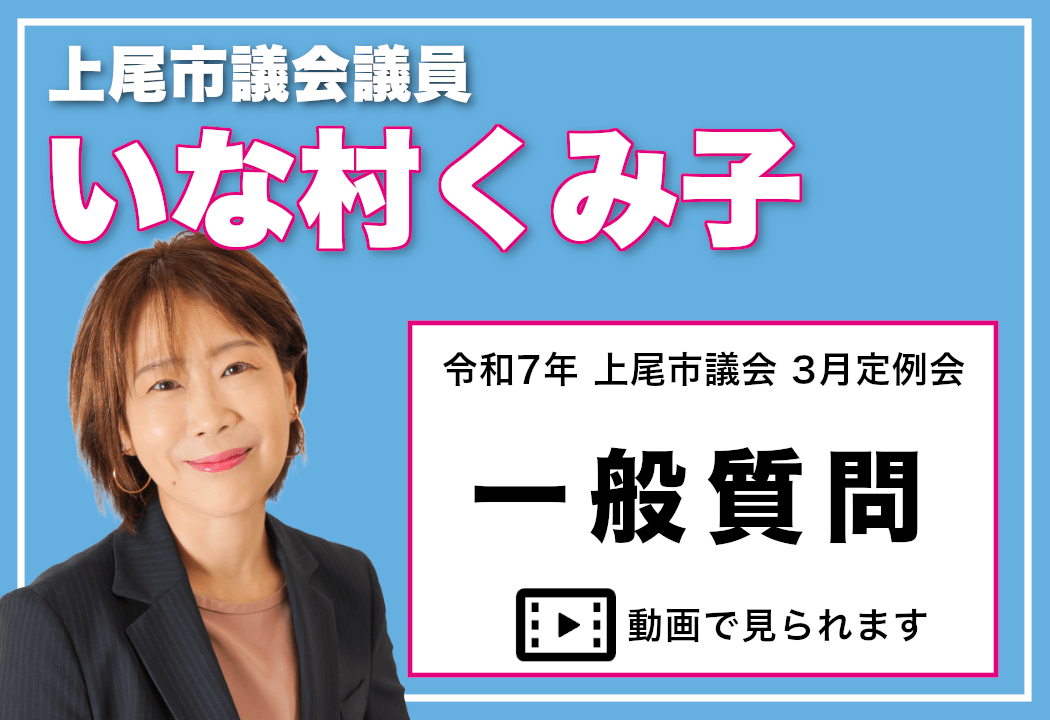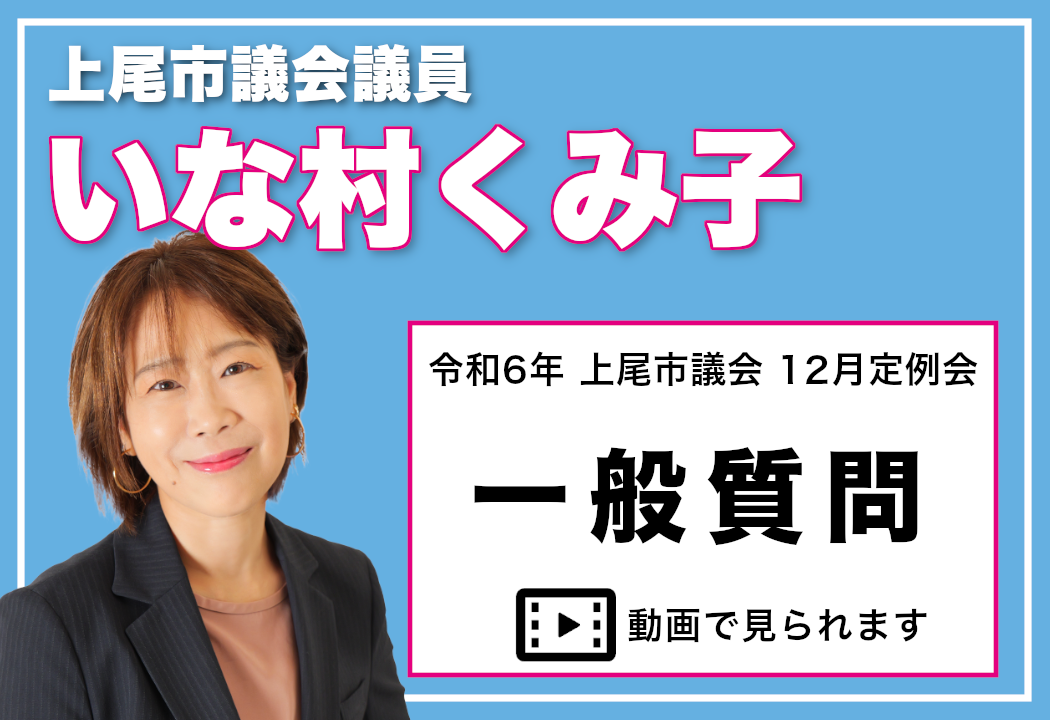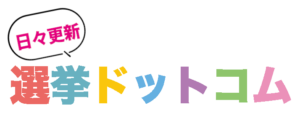こんにちは。上尾市議会議員、稲村久美子です。
今年は戦後80年です。ということで、平和学習について取り上げました。
その他に三つの質問をしていますので、ぜひお読みください。
質問事項
項目をタップ(クリック)で移動します

❶ 健康保険・介護保険及び予防について
(1)適正な服薬と医療費の抑制について
質問1-1-1)
医療費を抑制するために市はどのような取り組みをおこなっていますか。

答弁1-1-1)
上尾市国民健康保険では、医療機関からの診療報酬請求に対し、疾病名からみた検査や投薬間隔の妥当性や算定誤り等を確認する「レセプト点検」を実施しており、被保険者の方に対しては、医療にかかった履歴や費用等をお知らせするための「医療費通知」や後発薬品についての理解を深めるための「ジェネリック医薬品の使用勧奨通知」を発送するなど、医療費の抑制や適正な受診、服薬が行われるよう努めております。
なお、後期高齢者医療においても、埼玉県後期高齢者医療広域連合が同様の取り組みを行っております。

質問1-1-2)
重複・頻回受診や重複・多剤服薬を防ぐための取り組みはありますか。

答弁1-1-2)
「レセプト点検」に基づきまして、重複・頻回受診や重複・多剤服薬の可能性のある方に対し、状況確認の通知を送付し、適正受診や適正な服薬の啓発、指導、電話相談の案内など行っております。

2月に母が亡くなったのですけれども、退院後、在宅で介護をするとなったときに荷物を片づけていたらすごい量の薬が出てきました。
ビニール袋いっぱいの薬が幾つも出てきて、病院、クリニックを、自分の状態がおかしいと思いつつ、どうしていいか分からずにあちこち受診して、それぞれからたくさんの薬をもらってしまっていたわけです。
これらの飲みきれなかった薬は、捨てるしかありません。例えば便秘薬が4週間分、5週間分とか出ている。その必要性があるのかどうかというところに非常に疑問を持ちまして、当時も保険年金課さんに問合せをさせていただいたりしております。
本人は1割負担でしたので、そんなにたくさんのお金を払っていないというのもありまして、言われるまま薬をたくさんもらってしまう。結局飲まずに、というものがたくさんありました。
保険というのはやはり皆さんからお預かりしたお金を頂いていますから、例えば、一割負担の方が100円払ったとしても、実際1,000円であったりということを見える化して、自分がどれぐらいの医療費を使っているかということを、それぞれの方に知っていただきたいなというのがまず1点あります。
それとともに医療機関にも、お薬手帳を必ず確認して、重複した薬がないか、飲み合わせもそうですけれども、きちんと調べていただいてから薬を出してほしいというのがあり、今回の質問をやらせていただきます。
かかりつけ医やかかりつけ薬局というのを持つと、今言ったような話を防ぐことができると思います。

質問1-1-3)
かかりつけ医やかかりつけ薬局を持つメリットはなんでしょうか。

答弁1-1-3)
厚生労働省のホームページなどによりますと、日頃の健康状態を把握する、かかりつけ医がいることで、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になり、的確な診断やアドバイスを受けることができ、必要に応じて適切な医療機関の紹介を受けられるとされております。
また、かかりつけ薬剤師においては、服薬情報の一元的、継続的な把握と薬学的な管理をしていただくことで、多剤、重複服薬の防止や残薬の解消など適正な服薬ができるとされております。

かかりつけ薬剤師を持つメリット(かかりつけ薬剤師の3つの機能)
- ひとりの薬剤師がひとりの患者さんの服薬状況を一カ所の薬局でまとめて管理し、かつ、それを継続して行う機能(薬の専門家が身近にいるから安全・安心に薬を使用できる)
- 24時間対応を行ったり、患者さんの自宅にお伺いし在宅医療を行う機能(薬局が開いていない時間にも薬の相談ができ、在宅医療もサポートしてもらえる)
- 処方医や医療機関と連携する機能(医療チームのサポートを受けられる)
公益社団法人日本薬剤師会より引用
かかりつけ薬剤師、薬局とはということで、日本薬剤師会さんから資料をお借りしております。(こちらの資料をごらんになりたい方は「日本薬剤師会 かかりつけ薬剤師・薬局とは」でご検索ください)
かかりつけ薬剤師を持つメリットの3つの機能ということなのですけれども、まず専門家が身近にいるから安全安心に薬を使用できるという点、1人の薬剤師が1人の患者さんの服薬状況を1か所の薬局でまとめて管理し、かつそれを継続して行う機能というものがあります。
次です。24時間対応を行ったり、患者さんの自宅に伺って在宅医療を行う機能、さらにもう一つが処方医や医療機関と連携する機能ということで、お薬のプロにいろいろな質問ができます。私が在宅介護をやっているとき、薬剤師さんが家に来てくださいまして、状況がどんどん変わる中でも、この薬は飲み続けたらいいですか、どうですかというように相談に乗っていただきました。
このかかりつけ薬剤師を探すというのは手続がちょっと必要です。まずどうやって探すのか分からなかったら、自分がお薬をいただいたときに薬局さんに一声をかけていただいてということで手順を踏んでいただければと思います。

質問1-1-4)
どこのクリニックにかかったらいいかというのが分からずに救急車を呼んでしまったり、あちこちのクリニックにかかってしまったりということを防ぐために、不安なときに医療に関する相談ができる窓口というのはあるのでしょうか。

答弁1-1-4)
埼玉県が「医療安全相談窓口」を設置しており、医師等の対応についての相談や医療について説明が十分に得られないなどの相談、県内の病院についての相談を受けております。
また、医療機関の所在地を管轄する保健所でも相談を受けております。

ありがとうございます。
それでは、市販薬や処方薬の薬物依存の防止についてお聞きします。
オーバードーズという言葉を、みなさん聞かれたことがあるかと思います。
薬を大量に摂取してしまうということで、イメージとしては違法薬物というものが思い浮かぶかもしれませんが、ティーンエイジャーなどですと、市販薬や処方薬を大量に飲んでしまうということがあります。
ですので一部成分を抜いて販売されていたり、薬局は例えば2箱までしか買えないというような制限をかけています。
大量に市販薬を摂取することによって、違法薬物ではないですけれども、いろいろな作用があるわけです。そういうことがネットで簡単に調べられるのです。
手に入れやすいということで、子どもたち、特に若い子です。
試験勉強でちょっとくさくさするとか、寝られないというときにお薬を大量に取って、何となく気分が上がったような状態というのを繰り返す。
そういうものにはまってしまって、どんどん、どんどん薬が手放せなくなってしまうということが起きております。

質問1-1-5)
それについて市販薬や処方薬の薬物依存の防止については、上尾市ではどのような取組を行っていますでしょうか。

答弁1-1-5)
薬物依存の防止に関する市の取組といたしましては、今年度の「こころの健康講座」事業において、市販薬依存をテーマとした講座を10月に実施する予定でございます。
今後も、様々な事業を通じて薬物依存防止の啓発に努めてまいります。

質問1-1-6)
それでは薬物依存の防止に関する子ども達への教育はどのようなことを行っていますか。

答弁1-1-6)
薬物依存の防止に関する子ども達への教育につきましては、薬物乱用防止教室を学校保健計画に位置付け、学校薬剤師、警察職員等の専門家と連携しながら、年1回以上開催しております。

私は子どもが4人いるのですが、子どもたちはそういう教育を学校で受けてきました。
いわゆる違法薬物に関してはやられているのですけれども、今は市販薬ですね、敷居を下げて、あまり罪悪感を抱かないようなものにちょっとスライドしている部分もあります。
そこについてもまた手厚く教育現場でやっていただければなと思います。
やはり子どものうちからその危険性というのをしっかり知ることによって、依存状態にならないというのを、未然に防ぐというのが大事なことだと思います。これは要望とさせていただきます。
それでは、依存症治療後、依存症というのは症状です。
アディクションという専門用語があるのですけれども、これ1人でどうこうできるものではなかなかないです。
その治療がまず必要でありますし、その後のサポートがとても大事です。

稲村久美子から行政への要望!
質問1-1-7)
依存症治療後のサポート体制はどのようになっていますか。

答弁1-1-7)
健康保健センターでは、市民からの各種健康相談に関し保健師等が随時対応しておりますが、薬物依存症治療後のサポートにつきましては、疾病の特性から個別相談のほか、家族への支援も重要となってまいります。
本市では、家族支援の場として「ピアサロン」事業を実施しておりまして、家族相互のやりとりをグループ形式で行うことにより、家族に依存症への理解を深めていただくとともに、同様の悩みを抱える参加者同士の意見交換の場として活用いただけるよう、取り組んでいるところでございます。

依存症になってしまった後どうするか、非常に大切です。
また、市販薬とか処方薬というとどうしても危険であるという認識が薄くなってしまいます。
そこの情報交換というのはとても大事だと思います。隠し込むのではなく、相談できる場がたくさんあるというのが、防ぐというところにつながると思いますので、今後もぜひ活動を続けていただければと思います。
昔からこういったことというのはたくさんあったではないですか。手を替え品を替えではないですけれども、物が変わりながらということで、今は市販薬などが流行っている。
今回ちょっと質問では入れなかったですけれども、非常に危ないなと私なんかが思っているのがカフェインです。カフェイン量が非常に高いドリンク類、1本200円ちょっとで買えるものなのですけれども、それを1日に何本も、試験勉強のために飲むという子どもたちの話も聞きます。
違法なものではないではないです。ただ、これも依存になります。
カフェインというのは薬物ですので、そういうことも全て行政が早め早めに状態を把握していただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。

(2)介護保険サービスについて
質問1-2-1)
介護保険サービスを受けるにはどうしたらよいでしょうか。
これは3月にもやっているのですが、その後また市民の方から相談が来ました。
やはり分かりづらいということで再度よろしくお願いします。

答弁1-2-1)
介護保険サービスを利用される場合には、まず、市役所本庁舎2階の高齢介護課窓口や、各地域で高齢者の生活・健康・介護などの相談等に対応している地域包括支援センターにご相談いただき、要介護・要支援認定の申請を行っていただきます。
その後、市から介護認定の結果通知が届きましたら、介護度に応じてケアマネジャーまたは地域包括支援センターの職員と相談しながら、必要な介護保険サービスを記載した介護サービス計画書(ケアプラン)を作成し、計画書に基づいて介護保険サービスを利用いただくかたちとなります。

質問1-2-2)
介護認定申請はどのようにしたらよいでしょうか。

答弁1-2-2)
介護認定申請につきましては、市高齢介護課や、各地域の地域包括支援センターでお受けしております。
もし、外出が難しいなどの理由で窓口へお越しいただけない場合には、ご家族や地域包括支援センター職員による代行申請をご利用いただくことも可能となっております。

今お答えいただいたのが窓口へ行くのが難しい場合、家族や地域包括センター職員による代行申請ということですが、以前、 外出が難しい場合は自宅にも相談員が伺いますということもお聞きしています。
そういうことをもっと知っていただいて活用をしていただけるように、やはり周知に努めていただければと思います。
それで、次の質問へ行く前にちょっと1つお話ししたいのが、介護に関わる部分なのですけれども、上尾市のホームページは本当に見づらいです。
よその自治体のなども見させていただくと、やはり皆さん今はスマホで検索されますよね。
私もそうですけれども、小さい字って見づらいです。
また、たくさん情報が多過ぎてもピックができない、分かりやすくたどり着けるような工夫をしていただければと、これはちょっと要望とさせていただきます。
せっかくいいサービスがありますので。

稲村久美子から行政への要望!
上尾市ホームページをもっとわかり易く便利に!という要望を入れました。
質問1-2-3)
介護保険サービスについてどのようなサービスがあるか知りたい場合はどうすればよいか、また、その周知はどのようにされていますか。

答弁1-2-3)
介護保険サービスの種類や内容につきましては、申請窓口でご相談いただくほか、サービス利用の手引きである「上尾の介護保険」を作成しておりますので、この冊子をご覧いただくことでご確認いただくことができます。
この「上尾の介護保険」の冊子につきましては、申請窓口や支所・出張所等に配置しており、市のホームページにも掲載しております。
また、「介護保険のしくみ」をテーマとした出前講座を開催しておりまして、地域の集いの場などにお伺いして、制度全般のことやサービス利用方法等を説明させていただくなど、介護保険制度の周知に努めているところです。

質問1-2-4)
介護認定を受ける前に準備できることはありますか。

答弁1-2-4)
ご本人が、自分らしい、自分の望む医療や介護を安心して受けるために、日頃から家族や支援者と、今後のご自身のことや利用している医療機関や介護サービスなどに関する情報を共有しておくことが大切です。
市では、それら必要な情報を整理して記入しておくことができる「わたしノート」という冊子を無料でご提供しており、ご家族やご友人などとの話し合いのきっかけ作りにもご活用いただいております。
なお、介護保険サービスの種類や内容につきましては、サービスご利用の手引きである「上尾の介護保険」をご覧いただくか、高齢介護課や地域包括支援センターに介護保険サービスご利用のご相談をいただくことで、お知りになることが可能でございます。

上尾市ホームページより引用
先ほど小高議員へのご答弁でもありましたが、わたしノートということで、これなのですけれども、自分が分からなくなる前に書いておく。
これは自分だけではなく、自分と家族両方のためにあると私は思います。
うちの親は、割と勝手で両親とも自分が死んだ後のことなんか知るか、というような状態で、本当に亡くなった後何も分かりませんでした。
どこにお金があるか、どこに何があるか、どうしてほしいのか、全く分からないというのは、やはり残されたものというのはとても困ってしまう。
かつ皆さん今は自分のことではないと思っていらっしゃいますけれども、これは必ず、いずれ行く道ではないですか。
ずっと生きている人なんていないじゃないですか。
最後は弱って、最後は亡くなるということで、やはりこうやって事前に、このわたしノートという冊子がありますけれども、事前に自分の意思を伝えておくというのは、残った方たちへの配慮でもあるのかなと思います。
では次の質問に移らせていただきます。

質問1-2-5)
介護の初期段階の人が使えるサービスはどのようなものがありますか。

答弁1-2-5)
介護の初期段階の方がご利用いただけるサービスには、介護予防・生活支援サービス事業として、デイサービスなどの通所型と、ホームヘルプサービスなどの訪問型のサービスがございます。
なお、これらのサービスは、ひと月当たりの利用回数は異なりますが、要支援認定を受けた方のほか、要支援相当で認定を受けていない方もご利用いただくことができます。

質問1-2-6)
介護保険で受けられるサービスを具体的に教えてください。

答弁1-2-6)
介護保険で受けられるサービスのうち、ご自宅にお住いの方がご利用いただくものといたしましては、日常生活の手助けをしてもらう「訪問介護」いわゆるホームヘルプサービスや、介護施設に通って食事や入浴等をする「通所介護」いわゆるデイサービスがございます。 そのほか、自宅での生活環境を整える車椅子などをレンタルする「福祉用具貸与」や、自宅に手すりなどをつける「居宅介護住宅改修」などもございます。
また、ご本人の心身の状態によっては、介護施設に入所して介護サービスをご利用いただくことも可能です。
入所型の介護施設といたしましては、生活介護が中心である「介護老人福祉施設」いわゆる特別養護老人ホームや、介護やリハビリを中心とした「介護老人保健施設」のほか、認知症と診断された人が共同で生活し、食事や入浴などの介護や支援が受けられる「認知症対応型共同生活介護」いわゆるグループホームなどがございます。

質問1-2-7)
介護予防の観点から、介護サービスを積極的に利用することのメリットはありますか。

答弁1-2-7)
介護予防の観点からの介護サービス利用のメリットといたしましては、身体機能の維持・向上のほか、社会とのつながりを持つことによる孤立感の軽減や精神的な健康の向上、定期的にご利用いただくことで日々の健康状態を把握でき、異変があった際に早期に対応できること、ご家族の精神的・身体的なご負担を軽減し、安心にもつながること、などがございます。

(3) 健康維持・増進について
質問1-3-1)
各種健康診断には、どのようなものがありますか。

答弁1-3-1)
市が毎年実施している健康診断につきましては、胃がん、肺がん・結核、乳がん、子宮がん、大腸がん、前立腺がん、肺結核、肝炎ウイルス、骨粗しょう症、成人歯科健康診査、20歳代から30歳代ヘルスチェックがございます。
また、国民健康保険加入者には、40歳以上を対象とした「特定健康診査」や、後期高齢者医療制度加入者には、「後期高齢者健康診査」がございます。

質問1-3-2)
健康診断を受けるメリットについて教えてください。(予防の観点ほか)

答弁1-3-2)
健康診断を受ける最大のメリットは、病気の早期発見・早期治療が可能になることでございます。

早期発見、早期治療ということはやはり医療費を抑えるということにつながってくるわけです。
市としても早めに、今がんなんかも早めに分かれば治る、完治する場合が多いです。
病気というのはとにかく早く発見というのがとても大事なので、もっともっと健康診断をたくさんの方に受けていただければなと思います。

質問1-3-3)
健康増進について、どのような取り組みを行っていますか。

答弁1-3-3)
本年4月に策定いたしました「第3次上尾市健康増進計画および上尾市食育推進計画」では、生活習慣病の予防とともに、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上などに取り組むことで、健康寿命を延伸することを各分野の共通目標として掲げ、各種健康増進事業を推進していくこととしております。
その取組の一つとして、市民一人ひとりが日々の運動や食生活の改善、健康教室やイベントへの参加など健康増進へのきっかけづくりとして、手軽に楽しく、継続的に取り組んでいけるよう昨年7月から「あげお健康ぷらす」事業を展開しております。
そのほか、正しい歩き方で学ぶウォーキング講座などのイベント型運動講座や40~64歳を対象とした運動教室、健康に関する市政出前講座など、健康増進に向けた取組を実施しております。

大変丁寧なご説明をいただき、市がとても力を入れているということがよく分かりました。
先ほどもあげお健康ぷらすですか、アプリについて今日もお話出ていますけれども、こちらたくさんの方に登録していただければ、と思います。

質問1-3-4)
健康に不安を感じた際の健康相談窓口について教えてください。

答弁1-3-4)
健康保健センターでは、健康に不安を感じる方や、検診結果、生活習慣病の予防に関心がある方などからの幅広い相談について、保健師や精神保健福祉士、栄養士等が、随時、対応しております。
また、こころの不調を感じる方向けに、WebやLINEによる「いのちのオンライン相談」、精神科医による「こころの健康相談」、心理士による「こころの悩み相談」など、こころの健康保持に向けた相談にも対応しております。

❷ 児童および若者への行政の関わり

質問2-1)
市内中学生の中学卒業後の進路についてお聞きします。
令和6年度、中学を卒業後、高等専門学校及び特別支援学校を含む全日制高校に進む子と、夜間や通信制高校に進む子、専修学校に進む子及び就職する子、進路未定の子、それぞれの割合を教えてください。

答弁2-1)
令和6年度市内中学校を卒業した生徒の進路につきましては、高等専門学校及び特別支援学校を含む全日制高校への進学割合は89.7%、定時制及び通信制高等学校への進学割合は8.4%、専修学校への進学割合は0.3%、就職の割合は0.1%、進路未定者の割合は1.4%でございます。

この数字、予算委員会のときにお聞きして驚きました。
私が子どもの頃に比べて、やはり日本は豊かになっていて、進学というのが当たり前になっていると思っていたものですから。
1割の子が全日制には行かないのだなという部分がありまして、今回質問をさせていただいております。

質問2-2)
先日の予算委員会で、全日制高校に進学しない子の理由について「学びの多様化」といった発言がありました。
しかし現状としては、背景に義務教育期間から学校になじめないケースがみられます。
教育センターの学校適応指導教室に通う生徒の進路はどのようになっていますか。

答弁2-2)
令和6年度教育センターの学校適応指導教室に入級していた生徒の中学校卒業後における進路先につきましては、通信制高校や定時制高校に進学しております。

質問2-3)
全日制の学校に進学した事例はありますか。

答弁2-3)
これまで教育センターの学校適応指導教室に入級していた生徒の中学校卒業後における進路先には、全日制課程の高校に進学した事例もございます。

質問2-4)
一般的な進学の割合に比べ、全日制の学校に進学する子が少ない理由はなんですか。

答弁2-4)
全日制高校に進学する生徒が少ない理由といたしましては、通信制高校や定時制高校では、朝昼夜の三部制といった複数の登校スタイルや多様な課程・コースを選択できることから、個に応じた支援を受けながら、社会的自立に向けて学習できる環境に魅力を感じ、自分に合った進路先として選択していることなどがあげられます。

ちょっと要望になってしまうのですけれども、結局うちの教室(エイジア学習教室)なんかもそうなのですけれども、まず中学に通えなかった子が全日制高校にチャレンジするのって本当に敷居が高いです。
そういう子たちが朝起きているかというと大体お昼頃起きた、午後起きたと言う。教育センターなんかにもちょっと行ってもらったりしているのですけれども、その中で現実問題として全日制に行けるのだったら、それはそれで良いわけです。
本人たちが本当に何を望んでいるかというと、行きたいのだけれども、行けないという状態があります。
そこで小・中学校、やはり義務教育なので、ここの部分では不登校の状態にしない、ならないように周りがもうちょっと努力をしたり配慮をしたり、子どもたちへの投げかけ、しっかり子どもたちを見ていただければな、これは要望とさせていただきます。
学校を普通に、普通にという言い方は変ですけれども、小中義務教育に通えれば、それにこしたことはないと思っていますので、ぜひ今後もよろしくお願いいたします。

稲村久美子から行政への要望!
質問2-5)
不登校ということから、その状態になってしまう子もいるのですけれども、上尾市では、こどもや若者のひきこもり対策として、現在利用できるものにどのような事業がありますか。
又その対象年齢も教えてください。

答弁2-5)
ひきこもりやニートなど困難を抱えるこども・若者や家族からの相談に対しましては、こども家庭保健課の専門の相談員が対応しております。
また、自立に向けたこども・若者の居場所として、「ルームここから」を設置し、利用者の状況に合わせた自立支援プログラムを行っているところでございます。
「ルームここから」は、令和2年度の事業開始以降、利用者数が年々増加しており、令和6年度は延べ利用者数1,049人で令和5年度と比較すると約1.5倍に増加しております。
なお、「ルームここから」の利用は40歳に達するまでのこども・若者としてございます。

質問2-6)
ルームここからについて、利用者の方非常に増えているのですが、東西1か所ずつなど、場所を増やすことを考えていませんか。

答弁2-6)
令和7年度からは、開所日数を1日増やし週3日としたところでございます。
今後、利用者数の増加状況や利用者の声を聞きながら、必要に応じ検討してまいります。

質問2-7)
以前から質問や要望を入れさせて頂いている子どもや若者の居場所づくりについて、民間との連携は現在どのようになっていますか。

答弁2-7)
市と包括連携協定を締結している民間企業と、現在、協議を行っているところでございます。

協議を行っているということで、話は進んでいると捉えさせていただいてよろしいでしょうか。
子どもさんが公共スペースで勉強していたら、出ていけというようなことを言われたと相談を受けました。
今おうちの方も働いていたりしていて、誰かの家で勉強するというのも難しかったりします。
でも子どもたち、これから夏休みもありますよね。
集まって勉強しようかというようなこともあります。
本来は図書館に学習ルームがあれば、それで足りる部分もあると思うのですけど、そういうスペースは少ないです。
子どもたちが集まれる場所をつくってくださいと何度もお話ししているのはそういうことです。
子どもからすれば、ここにいるなと言われてどこに行ったらいいのかと、社会性という部分で、どうしても集まって何かをしたいということがあった場合、子どもたちのそこを叶えてほしい。
子どもの居場所って不登校の子などばかりではなく、全てです。
全ての子どもたちの居場所、公園ではない場所で、民間と企業との協議ということは、子どもが集まれる場所について進めてくださっている、と取ってよろしいですね。
ぜひよろしくお願いいたします。

❸ 平和学習について
「平和とは、戦争又は武力紛争がないことを必要とするのみならず、人間の安全保障、各国の主権及び領土に対する尊重、並びに対話及び連帯が奨励され、国内及び国際的な紛争が相互理解及び協力を通して解決され、
持続可能な開発がその全ての領域において達成され、生涯教育及び生活全体にわたる教育への普遍的なアクセス(緊急事態及び武力紛争におけるものを含む。)が提供され、
あらゆる形態及び要因の貧困(極度の貧困を含む。)が撲滅され、全ての者のあらゆる人権及び基本的自由が、いかなる例外もなしに、支持され、及び行動的な※グローバル・シチズンシップが奨励される、包摂的で民主的な及び参加型の手続が必要である。
世界的な課題に対処し、持続可能な開発を確保するために個人、共同体及び社会が変革的な行動をとれるようになるための教育の重要な役割及び「平和なくしては持続可能な開発はあり得ず、持続可能な開発なくして平和もあり得ない」ことを認め…
(以下省略)
※グローバル・シチズンシップ…誰もが地球社会の一員であり、そこに参画する責任を持つ市民だという意識
平和、人権、国際理解、協力、基本的自由、グローバル・シチズンシップ及び持続可能な開発のための教育に関する勧告 前文
文部科学省ホームページより引用
(1)学校での取り組みについて
今年は戦後80年です。
ということで、平和学習についてちょっと質問をさせてください。
資料に、まず平和とはどういうことか、ということが書かれております。
こちらをふまえて質問させて頂きます。

質問3-1-1)
義務教育中の学校教育での取り組みについてどのようなことをしていますか。

答弁3-1-1)
学校における取組につきましては、国語科や社会科で実施をしております。
具体的には、国語科では戦争や平和の尊さに関する物語文等を学ぶ中で、自分の思いや考えをまとめるなどの学習を行っております。
社会科では、戦争や現在も続いている紛争などについての歴史的な事実や、国際協調による世界平和の実現に努めることの大切さなどについて学習をしております。
また、埼玉ピースミュージアムと連携し、担当職員による出前授業を実施している学校もございます。
当時の水筒や防災頭巾、服、千人針、召集令状、焼夷弾のかけらなどの実物資料や写真資料を見たり触ったりしながら、戦時下の生活の様子について、学習を行っております。

質問3-1-2)
なぜそれを(平和教育)行う必要があるのか教育長としてのご意見をお聞かせください。

答弁3-1-2)
平和教育は、戦争や地域紛争の歴史及び背景などについて学ぶことで、戦争の悲惨さや命の尊さ、人権の尊重を理解し、国際社会の一員として平和な社会を築いていくことの大切さを学ぶものであります。
これらの平和教育は、児童生徒が持続可能な社会の形成者としての資質・能力を育成すために、必要なものであると考えております。

このような質問をいたします理由として、今、若い方が戦争について知る機会が減っているせいで、戦争というものの現実味が薄まっているのではないかと思っています。
2023年2月24日、西日本新聞にある記事が載っていました。
日本の20代の若者が、義勇兵になりにウクライナに行ってしまった。
これ私はSNSでその子のアカウントを見ていたのですけれども、結局2022年11月から更新がストップされてどうなったのかなと思ったら、やはり亡くなっていた。
日本人の若者です。
日本人の若者が義勇兵という名の下に戦地に行ってしまっているわけです。
日本からそういう子が出てしまっているのです。
だからこそ、戦争ってどんなものかしっかり教えなければいけないなと本当に改めて思いました。
彼も死ぬと思って行ったわけではないと思います。
ほかにもロシア軍に入隊し戦闘に参加している日本人もいます。
日本から参加してしまう、これは絶対止めなければいけない。
その上で、学校での教育というのはとても大切ではないかなと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。

稲村久美子から行政への要望!
(2)行政での取り組みについて
質問3-2-1)
上尾市では市民に対して、どのような取り組みを行っているでしょうか。

答弁3-2-1)
本市では、非核平和パネル展を中心に取り組んでいるところでございます。
パネル展におきましては、令和4年度からアリオ上尾を会場に加えたほか、令和5年度には展示物として市職員所有の実物資料の展示を開始いたしました。
また、周知方法としましては、これまで広報あげおやデジタルサイネージ等を活用していたことに加え、昨年度からは自治会掲示板や児童館での周知も行ったところ、過去最多となる981名の方にお越しいただいたところでございます。

質問3-2-2)
戦後80年を迎えることを踏まえて、市では今年度どのような取り組みを行う予定でしょうか。

答弁3-2-2)
戦後80年を迎えるに当たり、広く市民の皆様に戦争の悲惨さや平和の尊さについて考えていただく場を提供するため、8月30日に「平和コンサート・映画上映」を開催するほか、会場内では市内中学生による平和ポスターの展示も実施する予定でございます。
また、毎年開催している非核平和パネル展では、初めての取り組みといたしまして、市役所ギャラリー会場における「原爆被害等を模擬体験できるVRゴーグル」の体験ブースの設置を予定しております。
さらに、令和5年度からパネル展会場や児童館において実施している「千羽鶴プロジェクト」の集大成として、市民の皆様に折っていただいた千羽鶴を広島市へ寄贈する予定でございます。

質問3-2-3)
昭和32年発行の上尾町遺族会編「戦没者芳魂録」によると、今日までの上尾市出身の戦没者は750名と伺っております。
市では戦争を体験された方の記録を保有しているのでしょうか。
また、それらの記録保存はどのように行っていますか。

答弁3-2-3)
本市では、太平洋戦争中に日本国内外で過ごされた市民78名の方々から協力を得まして、当時の体験を執筆した文集「私の戦争体験」を、昭和56年から戦後40年にあたる昭和60年までの5年間にわたり発行し、現在も保有しているところでございます。
この文集「私の戦争体験」は、現在書籍として保存しておりますことから、今後の記録保存のあり方につきましては、他市の事例等も踏まえて、調査・研究をしてまいります。


先日行ったのですけれども、桶川飛行学校平和祈念館ということで、ここ改修工事をして公開されております。
こういったものというのは一度なくなってしまうと、また新たにということが難しいではないですか。
戦後80年というと、まだまだ戦争を体験された方がいらっしゃってお話を聞く機会もあると思います。
かつ上尾市で持っているその資料というものを今後後世に残していただきたいと思います。
桶川市ではこうやっていのちの伝言という形でこれも残しております。
1冊200円で、先ほどの平和祈念館で買えます。
上尾市でもぜひ市民の方に大戦の記憶を読める形になれば、ということで要望と今回はさせていただきます。

稲村久美子から行政への要望!
戦争体験などの記録を後世に伝える取り組みをもっと積極的に、という要望を入れました。
❹ 地域ラジオの活用について
質問4-1)
上尾市では、7月をめどに地域FMラジオ局が開局致します。
地域に根付いた情報発信の場として、上尾市ではどのような関わりを考えていますか。

答弁4-1)
本市において、コミュニティ放送局が開局するにあたっては、市民に対する情報伝達手段の多様化と即時性に寄与するものと考えられることから、市政情報の提供など可能な範囲で協力してまいりたいと考えております。

質問4-2)
豪雨時など防災無線が聞き取りにくいです。
他の自治体でも活用されており、安定して情報を得ることが可能な防災ラジオの導入について、上尾市ではどのようにお考えでしょうか。

答弁4-2)
防災行政無線については、聞き取りにくいとの声もいただいているため、メールマガジンやLINEによる放送内容の配信や、ホームページからのバックナンバーの確認に加え、インターネットのご利用が難しい方でも内容の確認ができるように防災行政無線の電話応答サービスも整備をしております。
また、令和6年度に株式会社ジェイコム埼玉・東日本 さいたま北局と「行政告知放送再送信に関する協定」を締結したことにより、同社の提供する有料の「防災情報サービス」に加入することで、屋内で防災行政無線の再送信を受けることができるようになりました。
防災ラジオにつきましても、情報配信の手段として、有用なもののひとつと認識しておりますことから、コミュニティエフエムとの連携も含めて、調査研究をしてまいります。

防災ラジオ、越谷では1台当たり2,500円の負担金で市が有償配布しています。
ほかの自治体でもやっているそうです。
防災ラジオ、緊急時にぽんっとスイッチが入ったりするなど、いろいろな機能がついたものがあります。
このようなことも有用ではないかなということで考えていただければと思います。
さらに、例えば広報として、越谷市では市長がラジオ談話室なんていうことで使われているわけです。
民間の事業に対してという話ではなく、ラジオというのは地域の、特に今回は地域の方に対して、限定して情報を発信できるということで、使いようはあるのではないかなと思います。
すごく人気が出てから上尾市が入れてくれといってもなかなか難しいので、またこの辺りは考えていただければと思います。
ということで、私の一般質問をこれで終わらせていただきます。

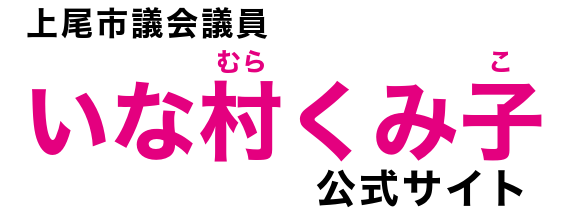
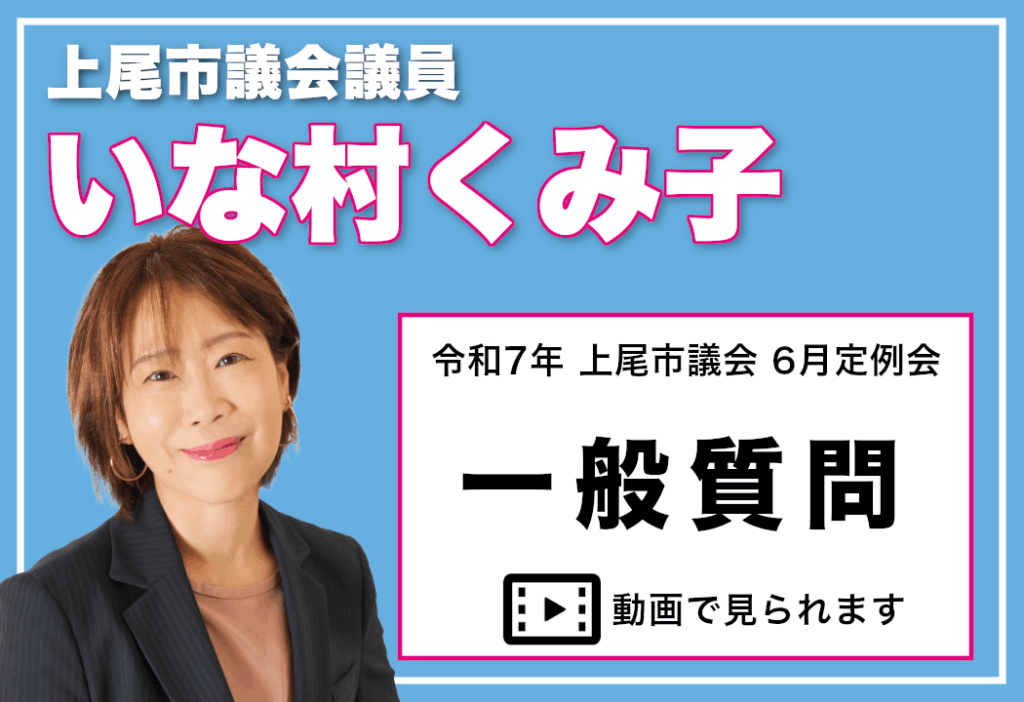
市政に対する政策要望書の提出.png)